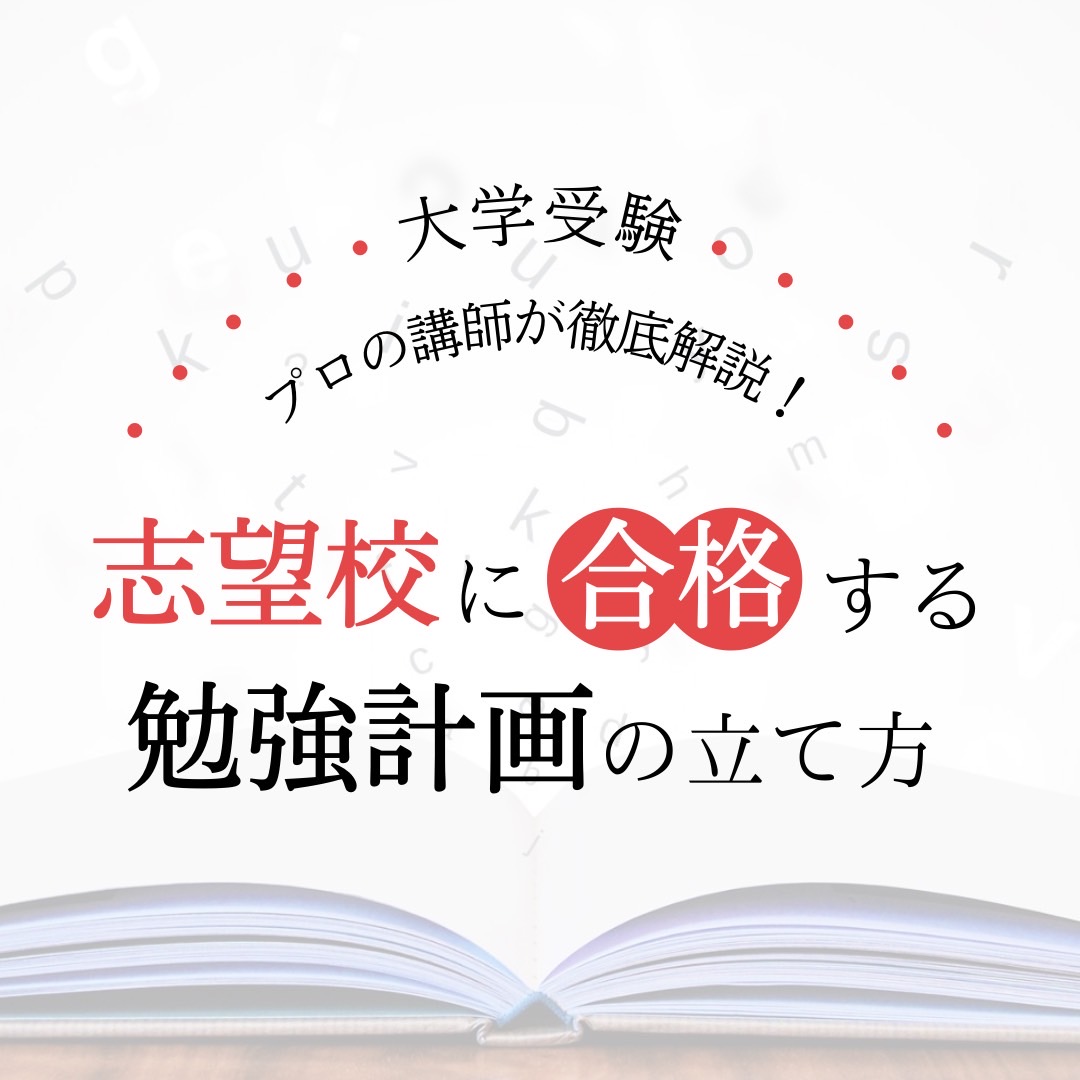大学受験でにおいて勉強計画を立てることは非常に重要です。志望校に受かるための勉強計画が有ると無いとでは結果は大きく変わってくるでしょう。しかし適当に作ったとしても意味がありません。今回は合格へと導く正しい勉強計画の作り方を徹底解説したいと思います!
登場人物紹介
コーチングプラス+の学習責任者。
受け持った生徒の9割が国公立に合格するという圧倒的指導実績を持つ。
コーチングプラス+の塾生。間違った勉強をしてしまうことがよくある普通の受験生。
そもそもなんで勉強計画が必要?
勉強計画が無くても勉強って出来るじゃないですか。別になくても良くないですか?
確かに無くても勉強はできるね。でも勉強計画があるとやらなければいけないことが明確になって勉強の質と量が激増するんだ!
勉強計画の意味
勉強計画を作成すると「いつ」までに「どの参考書」が「どのくらい」出来てなければいけないかが明確になります。
つまりただダラダラ勉強するよりも常に目的と目標を持って勉強することが出来るようになります。
長距離走で例えると、ただ1時間走ってくださいと言われるのと、10分間を時速10キロのスピードで走って2分間休憩を繰り返してください、言われるのでは後者の方がモチベーションを持って走ることが出来るということです。
また勉強計画を立てることは自分に合った勉強をすることにも繋がります。
勉強計画を立てないと行き当たりばったりで勉強をすることになります。
自分のレベルに合ってない参考書を解くとこになったり、時間のかかりすぎる問題集をやってしまったせいで、思うように成績が伸びなかったり、受験までに勉強が間に合わないという事態を避けることが出来ます。
勉強計画を立てる意味
①計画を立てることで目標を持って勉強することが出来る。
②自分のレベルに合った参考書や問題集を使って勉強することが出来る。
正しい勉強計画の立て方
勉強計画が重要なことは分かったけど、どうやって立てたらいいかわからないです、、
そんなこう君のために、今日は正しい勉強計画の立て方を教えましょう。
正しい勉強計画の立て方には3つのステップが存在します!
1つ1つ見ていきましょう!
ステップ1 今の自分のレベルを知る
今の自分の勉強のレベルを知ることは計画を立てるために一番大事と言っても過言ではありません。
なぜ今のレベルを知ることが重要かというと、正しい自分のレベルがわからなければ計画のスタートから挫折してしまう可能性があるからです。
例えば、早稲田大学志望のA君が勉強計画を立てたとしましょう!A君は今まであまり勉強していませんでした。しかし周りの早稲田志望の友達はみんな過去問を解いているので、なんとなくA君は勉強計画の最初に過去問を設定しました。
A君はこの後どうなるでしょう?おそらく過去問が難しすぎて全く解けず、勉強のモチベーションは下がり、勉強が嫌になってしまうかもしれません。
ではA君はどうすればよかったのでしょうか?
答えは意外と簡単で、マーク模試や、普段授業で使っている問題集の実践レベルの問題を解けばよかったのです。
そして模試の判定や点数を見るのではなくて、自分はどのレベルの問題をどのくらい解けるか?ということを明確します。
英語であれば、そもそも長文を解くのに英単語がわからなすぎる、世界史であれば知らない人物が多すぎる、というようなことに気付けると思います。そしたらまず最初にやるべきなのは単語帳や一問一答ということがわかります。
自分のレベルを知ることが出来れば、何から始めればいいかがわかります。まずは自分の勉強のレベルを知りましょう!
そしてそのために有効なのが、マーク模試や共通テストの過去問、普段授業で使う問題集に載っている実践レベルの問題です!前に解いた模試でもいいですし、共通テストの過去問はネットで無料でダウンロードできます!
ぜひ有効的に使って下さい!
ステップ1 まずは自分のレベルを知ろう
①レベルを知らないと最初から挫折する危険性がある
②レベルを知るために過去の模試や、共通テストの過去問を使う
ステップ2 今の自分のレベルにあったレベルの参考書を見つける
今の自分のレベルがわかったら次は今の自分にあったレベルの参考書を見つけましょう!
勉強計画において非常に需要なのは「どのレベルの参考書から始めるか」です!
最初に始める参考書を間違えてしまうと、勉強において最も重要な基礎や基本が身に付かないままどんどん次の参考書を進めていくことになってしまいます。
自分のレベルを踏まえて、見栄を張らずに参考書を選びましょう!
参考書のレベルは大まかに8段階に分けられます。
- 初学者レベル
- 定期テストレベル
- 受験準備レベル
- 共通テストレベル
- 中堅大学レベル
- 準難関大レベル
- 難関大レベル
- 最難関大レベル
1.初学者レベル
まだこの教科の勉強をほとんどしたことがないというレベル。本当に基礎の基礎から学ぶことが出来る。基礎に不安があるならこのレベルから。
2.定期テストレベル
学校や塾で習ったことはあるけど、忘れていたり、定期テストであまり良い点数を取れなかった場合はこのレベルから。
3.受験準備レベル
実際の入試問題よりもやや易しいレベルの問題。模試や共通テストの過去問を解くのはまだ早いという場合はこのレベルから。
4.共通テストレベル
共通テストと同じレベルの参考書。ある程度模試や共通テストの過去問に手ごたえを感じるようになっている人はこのレベルから。
多くの受験生の皆さんは1~4のレベルに該当すると思われます。
そのため冷静に自分の実力を見極めたうえでこの中から自分の始めるべき参考書のレベルを選びましょう。
ステップ2 今の自分のレベルにあったレベルの参考書を見つける
①参考書のレベルは大まかに8つのレベルに分けられる
②その中から今の自分に合った参考書を見栄を張らずに選ぶ
ステップ3 合格までに必要な参考書を把握する
現状のレベルと志望校に合格するためのレベルのギャップを埋めるために必要な参考書を全て把握します。
すごい大変そうですね、、
だからこそこれが出来れば勉強計画で回りに差を付けることが出来ます。
参考書を8段回のレベルで考える
今の自分のレベルが「3.受験準備レベル」だとします。そして志望校が「7.難関大レベル」だとします。
この場合3~7で5段階のレベルをクリアする必要があります。
- 初学者レベル
- 定期テストレベル
- 受験準備レベル
- 共通テストレベル
- 中堅大学レベル
- 準難関大レベル
- 難関大レベル
- 最難関大レベル
自分がクリアしなければいけないレベルを把握出来たら、次はそれぞれのレベルに当てはまる参考書を決定していきます。
例えば有名な英文法の参考書である「NEXT STAGE」はかなり重い内容になっていますが、「定期テストレベル」~「中堅大学レベル」までの4つのレベルをこれ1冊でカバーすることが出来ます。
「NEXT STAGE」が完璧になった後は「準難関大レベル」の参考書の「英文法ファイナル問題集」を扱います。
そして最後に「難関大レベル」である「頻出英文法・語法1000」を使って学習を行えば難関大レベルの文法力を手に入れることが出来ます。
このように参考書1冊1冊のレベルを把握して、それぞれのレベルに当てはめていけば自分に必要な参考書を把握することが出来ます。
参考書のレベルは参考書の表紙や冒頭に書いてあることが多いです。またAmazonのレビューやブログを参考にして、最後は自分の目で見て決めることも大事です!
ステップ3 合格までに必要な参考書を把握する
①自分の現在のレベルから自分の志望校のレベルまでの段階ごとに参考書を当てはめていく。
②参考書のレベルは参考書の冒頭に書いてあるので自分の目で見てチェックしてみましょう!
\プロ講師がオンラインで勉強計画を立ててくれる14日間の無料指導はコチラ/
しかし最も重要なことは計画を「実行」すること!
計画を立ててもなかなか実行出来ないんですよね、、
そうだね。だからこそ計画の実行をサポートしてくれる「コーチング」が必要なんだね。
コーチングプラスでは合格するために勉強計画を立てるだけではなく、立てた勉強計画を実行出来るようにプロの講師による「勉強法の指導」や「チャットによる勉強管理」を行います。
コーチングプラスの塾生の勉強計画の実行率は95%です。計画を立てるだけではなく、勉強を実行するところまでサポートしてほしいという方はぜひ2週間の無料指導を受けてみてください!
\プロ講師がオンラインで勉強計画を立ててくれる14日間の無料指導はコチラ/
コーチングプラスの14日間の無料指導を受ければあなたの「勉強が受かる勉強」に変わります!
まずは14日間の無料体験
無料体験でできること

勉強法や参考書の指導

今後の勉強計画の作成

勉強や進路の悩みを解決
最後に
ここまでこの記事を読んでいただきありがとうございます。
共通試験の日本史対策の役に立てていただければと思います。
コーチングプラス+ではこのような勉強法や参考書、入試についての細かいアドバイスを指導しています。
今年は偏差値を30上げて難関大に合格した生徒もいます。
2週間の無料体験ではこの記事以上の様々指導をすることができます。ぜひ無料体験を受けていただければと思います。
学習責任者 橋浦先生